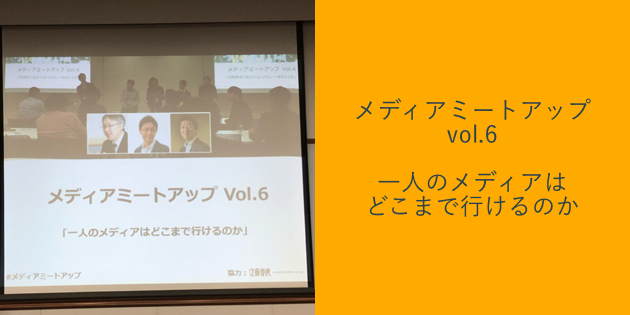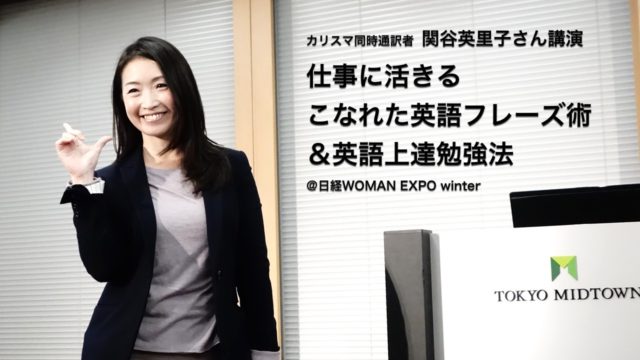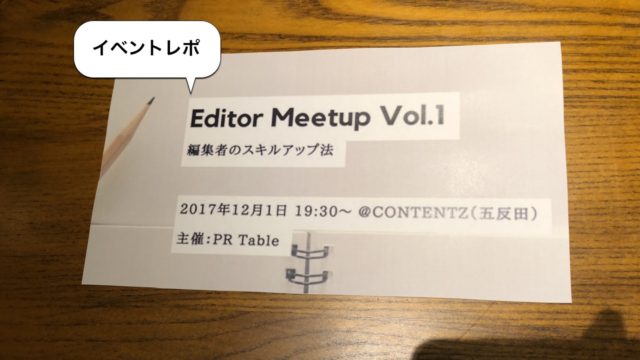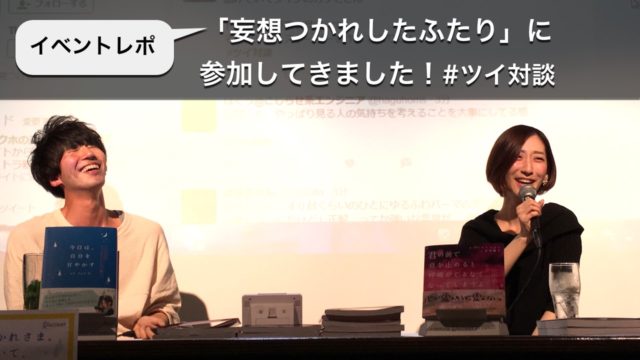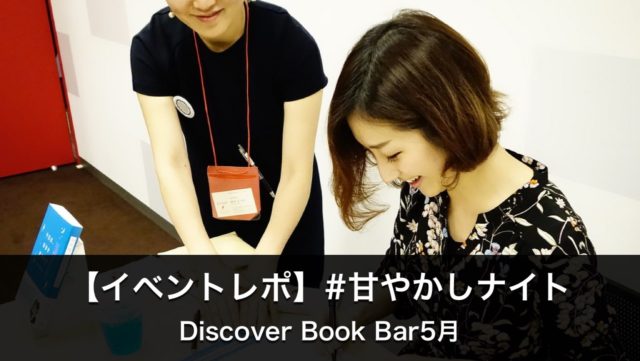今日は仲良くさせていただいている株式会社ゼスト社長の樫村さんが主催するグローバル人事塾という勉強会へ。
毎回会場・ゲスト講師が異なるのですが、今日は友人であり株式会社チェンジウェーブ代表の佐々木裕子さんがゲスト。
彼女とは数年前に出会ってから仲良くさせていただいていますが、仕事の話をきちんと伺うのは初めて。
自らを「変革屋」と呼ぶ裕子さん。
会社サイトからプロフィールを引用してみます。
東京大学法学部卒業後、日本銀行を経て、マッキンゼーアンドカンパニー入社。8年間強の間、金融、小売、通信、公的機関など、数多くの企業の経営変革プロジェクトに従事。退社後、株式会社チェンジウェーブを創立し、変革実現のサポートと変革リーダー育成に携わる。傍ら、自らの出産と同時に、子どもの可能性を引き出す託児サービス事業“creche bebe”を立ち上げる。
パッと見、「研修講師」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、微妙に違います。
研修はあくまで「ヘンカクを起こすための手段」とのこと。
(もちろん、結果として研修を企画・実施することも多いそうですが)
以前からスゴい人だなーと思っていましたが、今日の講演を伺って、ますますリスペクト!
さっそく内容をシェアしますね!
「場のデザイン」でヘンカクする
裕子さんが普段行なっている「場のデザイン」では、主に以下3つのステップを踏みます。
- 経営陣のディスカッションの場をつくる
- マネージャー陣に上の内容をおろす
- サポートメンバーはどこを理解して何をサポートしていくのか、を考える。
どういうチームであるべきなのかを議論する。
実際の現場ではファシリテーターだったり、講師だったりしますが、全体としては「場のデザイン」がメインの役割。
ちょっとしたキッカケで、人の視野や意識、世界の見方が変わることがある。
それを作っていく。
「音を立てて人が変わる瞬間」を作ると、化学反応のように周りも変わって、組織に変化が起き、世の中が変わっていく。
とおっしゃっていたのが印象的でした。
企業変革パートナーの仕事の本質
今日の講演内容、あまりに具体例過ぎて、どこまでオープンにして大丈夫なのか悩みましたが……事例の一部をシェアします。
たとえば、こういう依頼を受けたら(小売業の場合)
- 目的:次世代幹部育成
- 対象者:5年で店長・部長を目指せる人材(現在課長や主任ポジションについている)
- 内容:店長・部長に必要なスキル・ウィルを身につける内容。計3〜4回、1回1泊2日程度。
- 身につけさせたいこと:
1)経営手腕/経営視点 例)財務・戦略・マーケティング
2)使命感(自分たちが会社を変えていく)
上記のような依頼を受けて、裕子さんが行なった「場のデザイン」のステップは以下の通り。
1)TELして、依頼者にヒアリングをたくさんする
まずはニーズの把握から。
- どういうデータを見て仕事をしているのか?
- 「必要なスキル・ウィル」とは、財務会計の話?労務管理の話?全体の話?
など、自分が映像で見えるくらいまで具体的に質問をしまくる。
2)人事と一緒に社長と30分面談
次世代幹部=自分の後継者を育てたい、という想い。
それに対して、何が課題で、いま何が足りないのか? 究極、どうしていきたいのか?
社長の答えは「従業員間のコミュニケーション不足」とのこと。
「自分が声を大にして、言いたいことが言える&そういう風土を作れるリーダーが欲しい」
↓
では、なぜ「従業員間のコミュニケーション不足」がクリティカルなのか?
などなど、「そもそも」の話も含め、深くヒアリングするそう。
後半は割愛しますが、30分でココまで聞き出すのって相当大変なのでは……さすがです。
3)イケてる店長はいますか?ベンチマークになる店長は?
社長の想いを確認した後、今度は現場からヒアリング。
人事にベンチマークとなるような店長を紹介してもらい、その店長とTV会議。
その企業における意思決定のポイントをヒアリング。
すると、社長の認識を裏づけるように「自分の考えを本部にキチンと言えることが大事である」と分かります。
4)Toが分かったので、From(=研修の対象者の状態)を人事に聞く
人事に「彼ら(次世代幹部候補)はどんな気持ちで研修に参加するか?」を確認したところ、「自信満々で来ます」とのこと。
この研修をこなせば偉くなれるんでしょ?という感じだと把握。
↓
ではどうするか、となった際、裕子さんは「じゃあ最初に鼻っ柱を折らなくちゃダメ。どうやって折ろうか?」と考えたそうです。
5)360度評価をやってみる
「俺達できてる」→「やばい、全然できてない」と思わせる内容にしよう、と決めた裕子さん。
社長が求めるリーダーかどうか、部下から詳細にデータを取った上で本人に見せます。
「あなたの問題なのだ」とデータとして突きつけられないと、人は本気にならない、とのこと。
6)コンテキストを理解してもらう
「あなたの問題なのだ」と理解してもらう際のポイントが「コンテキスト」です。
何でこんなことをしなきゃならないのか? のコンテキストが分からないとダメだ、と裕子さん。
まずはマクロのデータで、何年後に人口が*%減る→割り出していくと自分の店の売上はいくら減るか。
それを回避するためには、どういうリーダーが必要か?を受講者の口から言わせます。
その上で、「じゃあ、そのリーダーは誰ですか?」と投げかける。誰か他の人ですか? あなた達ですか?
↓
「自分たちだ」とハラオチさせて、初めて360度評価のデータを見せます。
こうすることで、何が出来ていないのか? どういう固定回念が背景にあるのか? を自分で分析し、どういうリーダーになるか決めることができます。
上記を踏まえ、2日目にはケーススタディと実習を行ないます(ココでは割愛します)
事前準備も研修本番も、ものすごく大変なんだろうなと感じました。
これまでワタシが受けてきた研修とは何もかも違いそうで、話を伺ってるだけで何だか緊張しましたよ……!
ヘンカク屋の仕事≒リミッターを外す仕事

リミッターを外すのが仕事だという裕子さん。
よくある「リミッター」には3パターンあるそうです。
1)「思考停止」リミッター:「先がみえなくて不安」
⇒「よい問い」や「愛あるダメ出し」は、人の「思考停止」リミッターを外すチカラがある。
ダメ出ししてあげないと「このへんで良いかな」となってしまう
2)「固定概念」リミッター:「育児と両立しながら仕事を長く続けるのは無理」
⇒「これまで見えていなかった客観的事実」や「新たな生々しい実体験」が、それまではまっていた「固定概念」リミッターを解除していく。見ている世界を変える。
- 自分は客観的にどう見られているのか
- 他の人はどう生きているのか
- 実際やってみたらどう感じるか
3)「自己制止」リミッター:「しょせん、現状は変えられない」
⇒自分の内面と向き合い、心に従って「自己制止リミッター」を外すには、自分の変化に本気で期待をし、真剣に信じてくれる人が要る。
本日のマナビ!
裕子さんの話の中でグッと刺さった部分をご紹介します。
本当は、全てのことは絶対に変えられる。
世間が評価してくれるものでも、ToDoでもMustDoでもない、そこに向かっている自分が「心から楽しくてワクワク」する「目指したいもの」があれば、人はポテンシャルを最大限発揮できる。
ポイントは、自分たちが本当にそうしたい!という場を創れるか。
人と組織の変化を生む「場」を創るということ
人は、最後に左脳ではなく右脳。感情で動く。
だから、感情の部分に火をつける必要がある。
以下の文は講演中にも紹介されていましたが、まさに裕子さんの仕事は「心に火をつける」仕事なんだな、と思いましたよ!
The mediocre teacher tells. 凡庸な教師は支持をする。
The good teacher explains. 良い教師は理解させようとする。
The superior teacher demonstrates. 優れた教師はやってみせる。
The great teacher inspires. 本当に優れた教師は、心に火をつける。
– William A. Ward
■編集後記■
いやー、スゴかった!!!
普段、あまりの多忙さにグッタリの裕子さんを、これ以上痩せないよう食事にお誘いしてましたが、こんな大変なことをやっていたとは!
裕子さんに淡々と圧をかけて質問されたら、さぞかしコワいだろうな……とガクブルしましたよ……!
裕子さん、かっしーさん、参加者の皆さま、ありがとうございました!